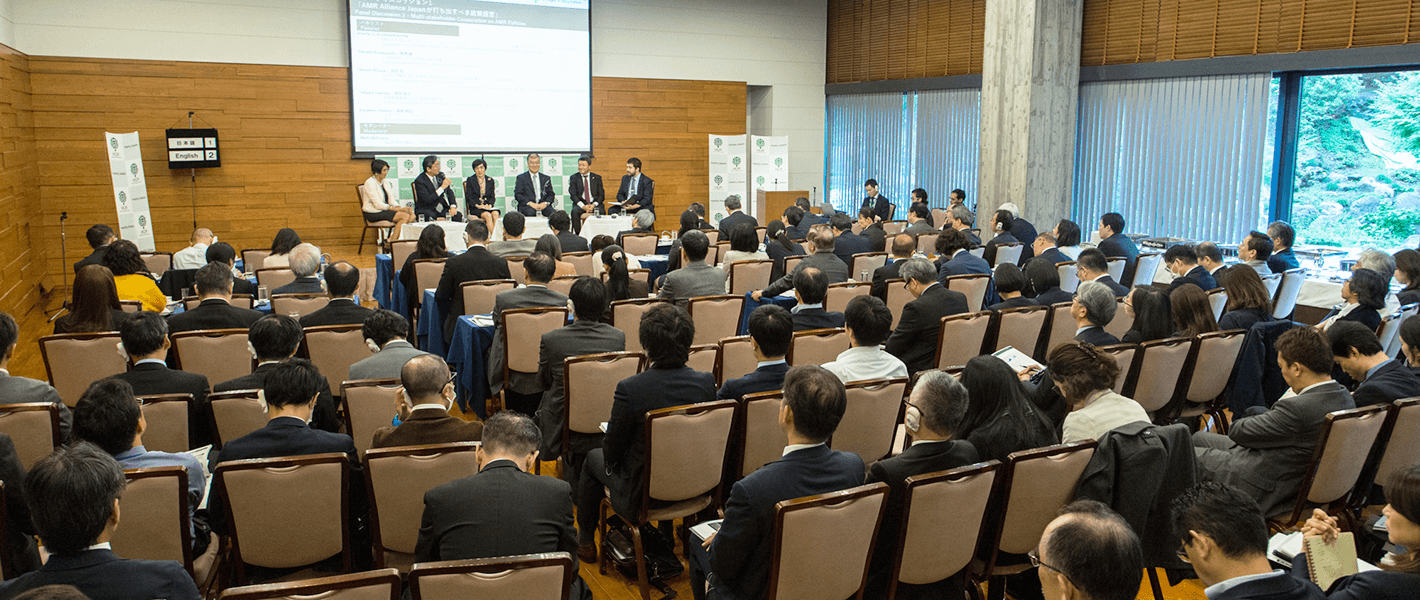【開催報告】第109回HGPIセミナー「小動物臨床現場での感染症とその未来を考えるー薬剤耐性の現状と対策・伴侶動物と新興感染症-」(2022年12月9日)
 今回のHGPIセミナーでは、むらた動物病院 院長/東京農工大学 農学部附属未来疫学研究センター 客員教授/獣医臨床感染症研究会 会長の村田佳輝氏をお招きし、小動物における薬剤耐性対策をテーマに臨床現場の現状やワンヘルスアプローチに基づく人獣共通感染症対策について、実際の臨床現場でのご経験やご研究をもとにお話しいただきました。
今回のHGPIセミナーでは、むらた動物病院 院長/東京農工大学 農学部附属未来疫学研究センター 客員教授/獣医臨床感染症研究会 会長の村田佳輝氏をお招きし、小動物における薬剤耐性対策をテーマに臨床現場の現状やワンヘルスアプローチに基づく人獣共通感染症対策について、実際の臨床現場でのご経験やご研究をもとにお話しいただきました。
<講演のポイント>
- 近年問題となっている新興・再興感染症はすべて動物由来であり、ワンヘルスの観点からヒト・動物・環境間の感染の連鎖が危惧されている。ワンヘルスとは、ヒト・動物・環境の健康は相互に密接に関わっており、全てを一体として捉える考え方である
- 小動物における薬剤耐性菌の増加が懸念されている。「薬剤耐性対策アクションプラン(2016-2020)」によって抗菌薬の使用状況等の把握が進み、農林水産省、日本獣医師会を中心に愛玩動物臨床獣医師が薬剤耐性の発生を意識して処方並びに行動していることが明らかになった
- 動物臨床現場では、細菌性膀胱炎の尿分離菌は腸内細菌群が半数を占めている。眼感染症の原因菌は、体表常在菌や口腔内常在菌が多く病態から検出された。これらは敗血症の患者検体からも多く検出される菌であり、生体内の免疫低下に伴い恒常性バランスが欠如することで感染を引き起こしていることがわかっている
- 動物における薬剤耐性菌は増加傾向にある。特に、MRS(メチシリン耐性ブドウ球菌属)とESBL(基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ)産生菌の保有が顕著である。MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)及びESBL産生菌はヒトと動物間の感染事例も確認されており、小動物における薬剤耐性対策では、獣医師等の処方する側による抗菌薬の慎重使用と飼い主等の処方される側の適切な抗菌薬使用の双方が必要である
- 獣医臨床感染症研究会(VICA: Veterinary Infection Control Association)では、感染症制御の概念の普及を目指して活動している。薬剤耐性対策としては、アンチバイオグラム作成、抗菌薬処方にあたる検査・治療ガイドライン作成、感染症ネットワーク確立等を積極的に実施しており、今後も広く展開される予定である。特に感染症ネットワークは東京農工大学・東京大学・国立感染症研究所・千葉県獣医師会等の地方獣医師会とともに協力関係にある。
■ 近年問題となる人獣共通感染症の脅威
人獣共通感染症とは、動物から人へ、人から動物へ伝播可能な感染症のことである。なかでも、近年問題となっている新興・再興感染症はすべて動物由来であり、ワンヘルスの観点からヒト・動物・環境間の感染の連鎖が危惧されている。ワンヘルスとは、ヒト・動物・環境の健康は相互に密接に関わっており、全てを一体として捉える考え方である。例えば、新型コロナウイルス感染症はクジラやイルカ等の海洋生物も感染しやすいと予測され、下水でもウイルスが確認されていることから環境への汚染も不安視されている。このことは薬剤耐性菌についても同様である。
また、新型コロナウイルス感染症はコウモリからヒトに感染し、さらに猫に感染しやすい(猫への感受性が高い)。そのためパンデミックの終息が、野生動物からヒトへ、ヒトから飼い猫へ、飼い猫から野生動物へといった感染の連鎖によって阻まれる可能性が懸念されている。クジラやイルカ等の海洋生物も感染しやすいと予測され、環境への汚染も不安視されている。他にも、急性熱性血小板減少症候群はシカやマダニからヒトへの感染が確認されており、エゾウイルス感染症やレプトスピラ症等も動物由来の感染症として日本国内で問題視されている。ESBL(基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ)産生菌はヒト(飼い主)と動物(小動物、愛玩動物)間での感染も危惧されている。またMRSAについてはヒトから動物に広がっていることも注意すべきことである。
人獣共通感染症対策の基本は感染源となる動物への適切な対応である。具体的には、排せつ物の注意深い処理や動物へのワクチン定期接種等が挙げられる。動物病院等の場合は、薬剤耐性の発生・拡大や院内感染を防止するために、スタッフは手指消毒やハンドクリームの使用等を通じて手荒れ防止に努めることが推奨される。飼い主の場合は、医師・獣医師の処方外で抗菌薬を使用しない、医師・獣医師の定める使用期間を守る、自己判断で投与を中断しない等が求められる。
薬剤耐性菌を作らない治療のために
―飼い主等処方される側が留意すること
- 投薬期間を守る
- 途中でやめない
- 飲んだり、飲まなかったりはしない
- 用法・容量の遵守
■ 小動物における抗菌薬の使用状況
近年、小動物における薬剤耐性菌の増加が懸念されている。動物の種類を問わず使用率と耐性率が比例関係にあることから、抗菌薬の過剰使用や誤用の可能性を踏まえた使用状況の把握が求められている。
日本の「薬剤耐性対策アクションプラン(2016-2020)」においても、医療機関での抗微生物薬使用量の動向把握と畜水産、獣医療等における動向調査・監視の強化が戦略として掲げられており、使用状況の把握は進んでいる。全国の伴侶動物病院を対象とした抗菌薬使用量の調査では全使用量(推定)のうち人体用抗菌薬が62%、動物用抗菌薬が37%、輸入抗菌薬が1%を占めることが判明した。一方、小動物に対する使用割合は第一世代セファロスポリン系が41%と最も多く、次いでペニシリン系が34%、ヒトにとって重要な第三世代セファロスポリン系やカルバペネム系の抗菌薬の使用は2%程度と極めて限定的であった。くわえて、医薬品卸売業界対象の調査では、愛玩動物における全約14トンの抗菌薬販売量のうち人体用が45.4%、動物用が54.6%であり、系統としては、第一世代・第二世代セファロスポリン系、ペニシリン系、フルオロキノロン系で販売量の半数以上を占めていることがわかった。以上の調査結果を踏まえると、愛玩動物臨床医師は薬剤耐性菌の発生を意識して処方並びに行動していると考えられる。ただし、第三世代セフェム系抗菌薬を第1選択薬としての使用および投薬が困難な患者に対する長期に及ぶ薬剤の使用(ロングターム薬の使用)に伴う薬剤耐性菌の発生は懸念である。
動物用抗菌薬を取り巻く制度も改善している。平成26年に実施された「薬事法関係事務の取扱いについて」の一部改訂によって、既に獣医療現場で汎用されている人体用医薬品を小動物用医薬品として製造販売承認申請をする場合は特例的に臨床試験を簡略化できるようになった。そのため、犬及び猫への使用実績がある人体用医薬品を動物用医薬品に転用し、動物用抗菌薬の開発・販売を一層推し進めることが可能である。この特例を適用した際は、承認2年以内を目途に有効性及び安全性に関する情報の収集とその提出が求められるため、抗菌薬の慎重使用・適正使用の更なる推進と販売量把握にも資する制度といえる。小動物専用薬の少ない現状においては朗報である。
■ 小動物臨床現場における分離菌の実態と薬剤耐性菌の現状
院長を務めるむらた動物病院では、犬、猫共に細菌性膀胱炎の尿分離菌は腸内細菌群が半数を占めている。病院が日常的に連携する検査センターによる小動物を対象とした細菌性膀胱炎の検査でも、疾患を引き起こす尿検出菌は大腸菌が最も多い。大腸菌の他にも肺炎桿菌、プロテウス・ミラビリス菌、ブドウ球菌インターメディウスグループ、アグラーゼ陰性ブドウ球菌が検出されており、どれもESBL産生菌やMRS(メチシリン耐性ブドウ球菌属)の薬剤耐性菌が多く分離された。
むらた動物病院では眼科も標榜しており、眼感染症(細菌性結膜炎や角膜炎等)の分離菌はブドウ球菌インターメディウスグループが最も多かった。同検査センターが実施した犬及び猫を対象とした眼感染症の分離菌では、犬は表皮から落下した体表常在菌が多く、猫では口腔内常在菌が多い。手を舐めて顔を洗う猫の習性が影響していると考えらえる。
また、むらた動物病院における敗血症の血液培養では、2009年から2014年までの全216症例中40症例が陽性(菌血症)であった。感染の原因疾患としては、腎孟腎炎が最も多く、次いで動物特有の子宮蓄膿症等の免疫介在性疾患が報告されている。膀胱炎と同様に、分離菌は大腸菌等の腸内細菌群が多く、カンジダ属菌種も検出された。子宮蓄膿症の場合も、検査材料(血液、子宮・腹水膿)の種類に依らず、大腸菌が多く分離される傾向にあった。小動物において敗血症は、生体内の免疫低下に伴い恒常性バランスが欠如し、バクテリアルトランスロケーションが成立することで感染する。バクテリアルトランスロケーションとは、腸内細菌が腸管上皮の粘膜バリアーを通過して腸管以外へ移行し、全身感染を引き起こす現象を指す。元来、腸内には多量の細菌が共生しており、腸内細菌叢(マイクロバイオーム)を形成して様々な免疫に関与している。そのため、腸管免疫のコントロールには腸内環境の改善が重要である。
小動物で見られる薬剤耐性菌は主にESBL産生菌とMRSの2種類であり、MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)は比較的まれである。むらた動物病院が日常的に連携する検査センターによる犬・猫の耐性菌分離検査では、大腸菌のESBL保有率が40.8%、ブドウ球菌インターメディウスグループのMRS保有率は57.5%である。特に、MRSの保有率は2005年の調査開始から年々上昇傾向にある。さらに、真菌症では特にカンジダ症で多剤耐性菌が多く分離している。真菌(真核生物)は細胞構造的が近いため、ヒトへの感染も強く危惧される。前述の通り、ESBL産生大腸菌はヒト(飼い主)と動物(小動物、愛玩動物)間の感染も危険視されている。MRSAは飼い主から愛玩動物に感染した事例も報告されており、今後はワンヘルスに基づく公衆衛生上の総合的なモニタリングが必要である。
■ 獣医臨床感染症研究会(VICA)による薬剤耐性対策と今後の展望
2013年に臨床獣医師の有志で獣医臨床感染症研究会(VICA: Veterinary Infection Control Association)を設立した。VICAの理念は、小動物における、臨床に即した感染症のデータの蓄積と感染制御の普及啓発である。特にAMRと敗血症に注目し、感染症制御の概念に基づいた活動を進めている。
感染症制御の概念
- 感染症の知識を持ち啓蒙する
- 感染症を予防する
- 感染症を作らない
- 感染症を広げない
- 感染症を効率よく治療する
VICAが進める薬剤耐性対策の具体的な試みとして、動物病院内におけるアンチバイオグラムの活用がある。アンチバイオグラムとは、病院内で検出された各細菌の抗菌薬の感受性率を集積し、図表化したものである。VICAでは会員病院を対象に施設単位のアンチバイオグラムを作成し、広域抗菌薬の慎重使用を促進することに成功した。フルオロキノロン系、第三世代セフェム系、四世代セフェム系、カルバペネム系抗菌薬の使用制限、複数剤の併用によるスペクトラムのカバー、周術期等の予防的抗菌薬の使用制限が推進され、その結果、MRSP(メチシリン耐性菌)とESBL産生菌の減少、テトラサイクリン系とフルオロキノロン系薬の耐性率が減少した。この成果は論文等でも報告されている。
小動物臨床の現場で薬剤耐性菌を作らない治療を進めるために、これからはVICAが策定に注力している抗菌薬決定のための検査・治療ガイドラインと併せて、アンチバイオグラム作成の取り組みを広く展開する予定である。
薬剤耐性菌を作らない治療のために
―愛玩動物臨床獣医師等等処方する側が留意すること
- 第一選択薬はペニシリン系、第一世代セフェム系抗菌薬を使用
- 広域抗菌薬の慎重使用
- 周術期などの予防的抗菌薬はペニシリン系やセフェム系第一世代抗菌薬を短期間(1回-4日)で使用
- グラム染色、薬剤感受性試験の利用を慣行
- デエスカレーション療法の実施
- 小動物臨床での抗菌薬使用ガイドラインの整備
また、VICAでは感染症ネットワークの確立も進めている。千葉県では、千葉県獣医師会、国立感染症研究所、東京大学、東京農工大学が中心となり、千葉県感染症ネットワークを構築している。VICAでは、日本獣医師会や地方獣医師会の協力のもと、このネットワークの全国展開を推進している。検査センターと協働して各地の動物病院からの情報を収集することで、将来的には小動物臨床の感染症情報をリアルタイムで一元的に管理する仕組みを構築しようとしている。
ワンヘルスというヒト・動物・環境の健康は相互に密接に関わっており、全てを一体として捉える考え方を実現するためには、領域横断的な連携と協働が今まさに求められる姿勢である。ワンヘルスアプローチに基づいて小動物における感染症対策を進めることが人獣共通感染症や薬剤耐性菌の制御に繋がり、より良い未来に貢献する。
【開催概要】
- 登壇者:村田 佳輝 氏(むらた動物病院 院長/東京農工大学 農学部附属未来疫学研究センター 客員教授/獣医臨床感染症研究会 会長)
- 日時:2022年12月9日(金)19:00-20:15
- 形式:オンライン(Zoomウェビナー)
- 言語:日本語
- 参加費:無料
- 定員:500名
■登壇者プロフィール:
村田 佳輝 氏(むらた動物病院 院長/東京農工大学 農学部附属未来疫学研究センター 客員教授/獣医臨床感染症研究会 会長)
1980年北里大学獣医学部獣医学科卒業、1982年同大学院獣医学修士取得、さわき犬猫病院を経て、1984年からむらた動物病院院長を務める。2009年千葉大学大学院医学薬学部にて医学博士を取得(医真菌学)する。国内外で、ペットに関する感染症関連の論文・本を多く執筆する。2013年に発足された小動物分野における臨床感染症の専門家集団である獣医臨床感染症研究会(VICA)では会長と務め、2019年AMR対策の優良事例として内閣官房の「AMR対策普及啓発活動表彰」を受賞する。ペットから分離される薬剤耐性菌の実態調査や、獣医師向けのガイドライン作成などに取り組み、抗菌薬の適正使用・慎重使用の重要性について学会や連携シンポジウム、症例検討会、各種専門誌への投稿などを通じて普及啓発・発信を行ってきた。ペットの臨床現場においてヒト・動物・環境のワンヘルスを考慮しながらAMR対策を進めている。